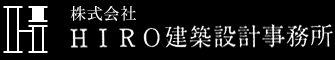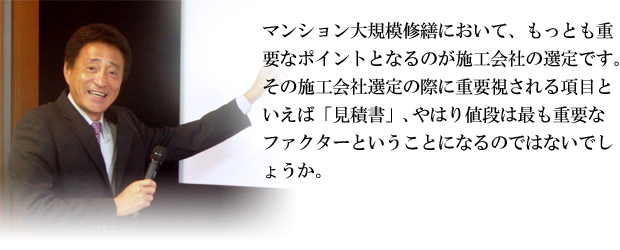
管理組合で工事の見積を元に協議しながら施工会社を決定する「見積合わせ方式」が一般的に採用されているものです。
「見積合わせ方式」では、まず提示された見積を、現場説明などを通じて設定した見積条件と照らし合わせ、食い違いがないかを確認します。そして、使用する予定の工法・材料、金額(単価)などの面での比較検討を行うだけでなく、見積に参加した会社の会社規模、施工業務体制、施工後のアフターフォロー体制、工事施工実績とその内容評価などを加味し、必要に応じて面談を実施するなどして、総合的に評価し選定していきます。
つまり、「見積合わせ方式」では、必ずしも最安値を見積した会社が選定されるとは限らないため、いわゆる「入札方式」の方法とは全く方式が異なります。
建築分野というと、理解するには専門知識が必要で「難しくて分からない」というイメージが先行しがちですが、ここでは分かりやすく簡単にいってしまうと、工事費は
|
A
|
直接工事費(材料費・施工費・加工費・運搬費)
|
|---|---|
|
B
|
共通仮設費(現場事務所や水道・電気の準備など工事用地のセッティング費用)
|
|
C
|
諸経費(現場経費や会社の一般管理費などで営業利益を含む)
|
で構成されています。
しかし、これらの項目で見積をとったとしても、各社それぞれ異なった金額の見積が出てくることになります。同じマンションに対しての見積なのにどうしてこんなことになるのでしょうか?
手元に届いた見積は、各社下記のような違いが生じているはずです。
A 直接工事費の違い
「数量の違い」
数量の指定がない場合は、建築数量積算基準などをもとに各社で算出してきます。実際に工事に必要な量(切り無駄ややむを得ない消耗を考慮)で算出されるため計算方法も違い、設計数量とも異なることもある。修繕工事においては、工事範囲の読み違いで数量を誤る可能性もあります。
「材料単価の違い」
仕入先や調達方法、数量によって異なる。指定のない材料のグレードが異なることがある(通常は指定がない場合、中庸晶を用いる)。
「施工費の違い」
「加工費の違い」
「運搬費の違い」
労務をどのように捉えるかで異なる。難しい、ややこしい、日数のかかる作業などと想定すればもちろん高くなる。施工上必要な資材、道具、特殊技術・特許技術の有無によっても異なります。材料費と労務費を合わせた複合単価として計上する場合もあります。
「直接仮設費の違い」
主に足場や落下防止等の措置で、現場の安全性・作業性により異なる。
B 共通仮設費の違い
現場の空間的条件、工事の規模(作業員の数)、工事期聞によって異なる。
C 諸経費の違い
労働者雇用や会社運営にかかわる費用が含まれ算出が困難なため、一般的に工事費に率をかけて算出する。(国土交通省『公共建築工事積算基準』等参照)
ざっと、こんな感じでしょうか。
これは各社が、今回の大規模修繕工事をどのように捉えているか?
どこを優先的に工事して、どこを工事しないで良しとするかといった認識・判断が見積の中に反映されているのです。
見積が適正かどうかを判断するには、設計図書と見積要項書の内容がすべて頭に入っていなければなりません。また、実際に行われる工事の手順がイメージできなければ「なぜそのような手間賃がかかるのか、そのような資材が必要なのか」は分かりません。
つまり、工事項目の小計金額を比較しただけでは、見積内容が適正かどうかは判断できないのです。
私たち設計事務所は、プロとして見積書の詳細を見て施工会社がどのように工事を捉えているかを読み、その会社の力量を推測します。特に修繕工事は新築工事と違って「居住者のいる現場」ですから、要求された質の工事を安全かつ短期間に合理的に計画したところが適切な工事費を算出しているといえるでしょう。一方、不確定要素が多くある、居住者の対応が不安、などという仕事に対しては、リスクを考え、高く見積もる可能性もあります。工事費を抑えるためには管理組合の協力が欠かせません。こうした際にも設計事務所はガイド役をつとめ、相互に協力出来る体制づくりのサポートを行っていきます。